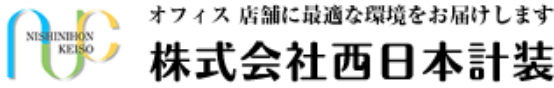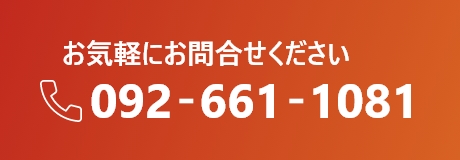会社情報 -COMPANY-
- 商号
- 株式会社西日本計装
- 設立年月日
- 昭和41年10月21日
- 代表
- 山内 辰崇
- 資本金
- 1,000万円
- 所在地
- 〒813-0043 福岡市東区名島5丁目41番13号
- TEL/FAX
- TEL:092-661-1081 FAX:092-661-1924
- 事業内容
- 計装、電気工事、動力工事、冷媒配管設備工事
- 工事事業者登録
- 電気工事業者届済票 福岡県知事登録 第47029号 一般建設業許可 福岡県知事 許可(般1) 第22245号
- 取引銀行
- 福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行
- 所属団体
- 電九協福岡電設協同組合、福岡県電設協力会、福岡市電設協力会、東福岡法人会
- 主要取引先
- 株式会社菱熱、東洋熱工業株式会社、株式会社朝日工業社、大橋エアシステム株式会社、株式会社九電工、JR九州電気システム株式会社、福岡県、福岡市
- 仕入先
- 株式会社カンサイ、三興バルブ継手株式会社、株式会社プレナム機工、株式会社朝日酸素商会、東芝電材マーケティング株式会社
沿革-HISTORY-
~こんな感じで西日本計装は産れました~
時は遡ること昭和8年、現在の福岡市東区名島に当時では日本最大級の橋「名島橋」が完成しました。
おおらかな7連のアーチを描き、白く輝く御影石に覆われ、力強い美しさを感じさせてくれました。 しかし12年後の昭和20年、大東亜戦争の際、白く大きな名島橋は空襲時に目立つという理由から黒いタールで塗装されることになり約10年の間、名島橋は白い橋から黒い橋に変貌していました。
そこから再び年月が経ち、昭和30年代。 天皇陛下が福岡にお越しになるということで、コールタールを塗った黒い橋ではだめでしょうって話になったそうです。 私の祖父である「山内熊雄」は石工をしていた関係で、橋を黒く覆ったコールタールを剥がして、元の白い御影石の橋に戻してほしいと依頼がきたそうです。 祖父熊雄はハンマーとノミを持って早速仕事を始めますが、なんせ全長204m全幅24mの巨大な橋です。全てを削り工期内に終わらせるにはハンマーとノミではダメだと思った祖父は知人から電動グラインダーを借りたそうです。 しかし当時は周囲に建物等が無く電動グラインダーを動かすための電源が用意できなかったそうです。そこで思いついたのが盗電だったそうです。 橋の両端には電柱があったので、祖父と私の父であり後の㈱西日本計装の創業者である「山内竟司」と二人で電柱によじ登り、電線を繋ぎ、まんまと盗電に成功して電動グラインダーを使用して、元の白い名島橋に復元したそうです。 その時の経験から、父竟司は電気工事は面白い、これからは電気の時代と考えたそうで九州電気工学専門学校に通い卒業後地元の電気工事店に就職しました。 その後九州電気工事(株)(現(株)九電工)で電気工事の職人として働いました。
ある日仲の良かった同僚が「東京に行ったら倍の給料がもらえるらしかぜ」とどこかで話を聞いて、「そげな事なら東京に行こうや」ってことで同僚の方と二人で上京したそうです。 東京でお世話になった会社が山武計装(株)の下請けをしている会社で、父は当時山武計装の会社に毎日のように出入りしていたようです。 その頃の山武計装の工事課長が大の将棋好きで、父と毎日のように将棋をしていたそうです。(父もかなりの将棋好きでした)その課長さんが「今度九州に山武計装の営業所を出すから山内君も九州に帰って自分で会社を作って山武計装の仕事をやりなさい」ってことで昭和41年に福岡市東区香椎に(有)西日本計装を設立しました。